とにかく変化が多い4月!大きな環境の変化がない方にとっても、周囲がせわしなくなりがち。ひと月頑張れば月末からはGWへ突入することから、無理をして五月病につながる方も少なくありません。
五月病予防は4月の過ごし方がカギ!産業保健師が教える、心と体を守るために4月に意識したいこと
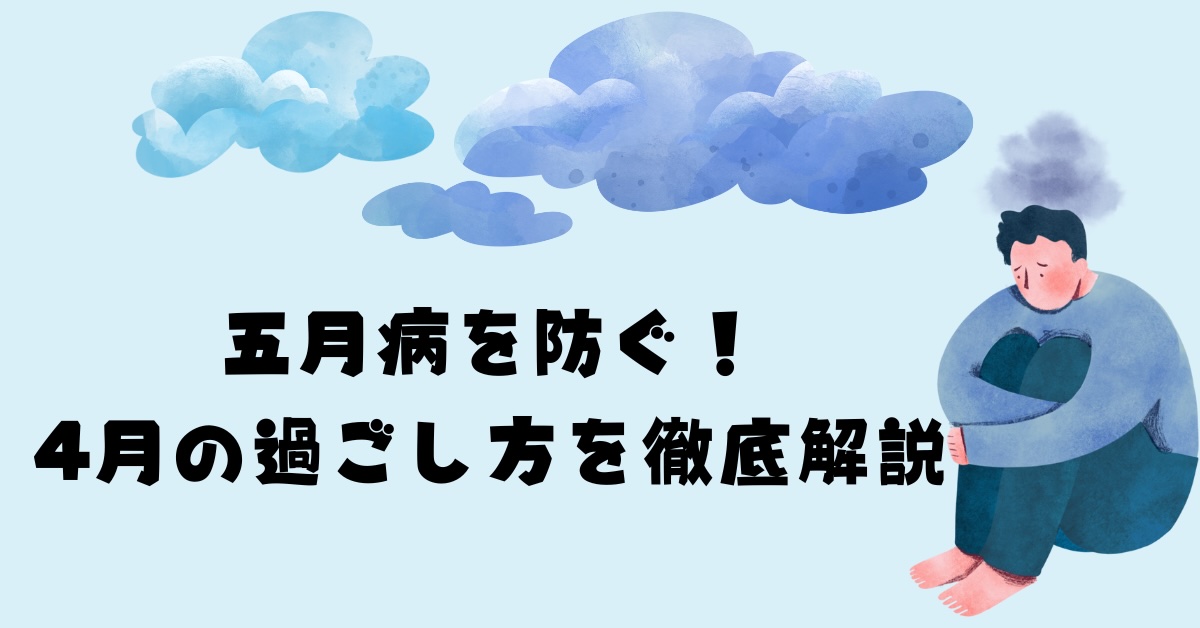 健康に関すること
健康に関すること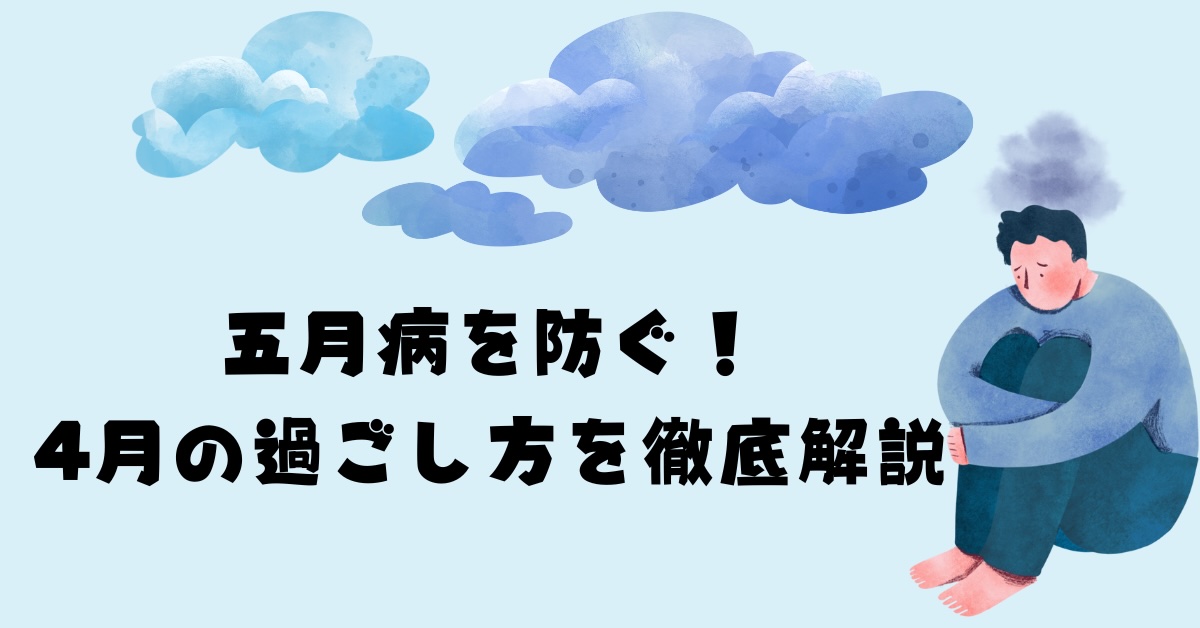 健康に関すること
健康に関することとにかく変化が多い4月!大きな環境の変化がない方にとっても、周囲がせわしなくなりがち。ひと月頑張れば月末からはGWへ突入することから、無理をして五月病につながる方も少なくありません。
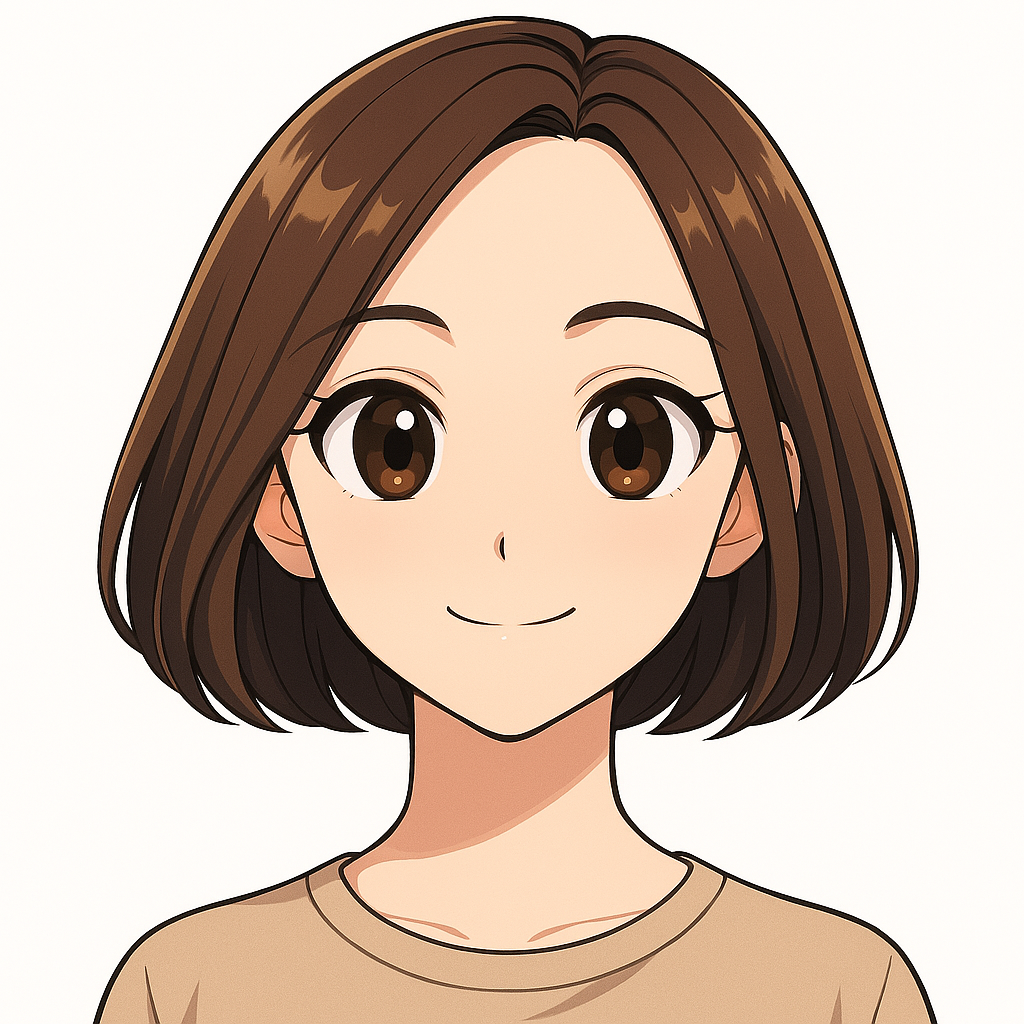
エネルギーを消耗しやすく疲労を蓄積しやすいこの時期を上手に乗り切り、元気に5月以降も過ごせるヒントをお伝えします。
五月病とは、4月に始まった新生活のストレスや環境の変化によって、ゴールデンウィーク明け頃から心身の不調が現れる状態のことを指します。医学的な病名ではありませんが、「やる気が出ない」「眠れない」「疲れが取れない」「学校や職場に行きたくない」などの症状がみられ、多くの人が経験する可能性があります。
新年度は、学校や職場での新しい人間関係、新たな業務や責任、生活リズムの変化が一気に押し寄せるタイミングです。知らず知らずのうちにストレスが蓄積され、体調や気分に影響を及ぼすことがあります。

4月は気圧の変化が頻繁に起こりやすい時期です。
この時期は季節の変わり目であり、移動性高気圧と低気圧が短い周期で交互に日本付近を通過するため、天気や気温が安定せず気圧の変化が頻繁に起こります。
今年も、桜が咲くほど暖かく薄いシャツ1枚で過ごした日があったと思えば、翌日には冬のような寒さに逆戻り、といったことがありました。
気圧と体調の変化に敏感な方にとっては辛い時期の一つです。
参考:ウェザーニュース
4月は、入学・進学・就職・異動・転勤など、生活環境や所属するコミュニティが大きく変化する節目です。新たな人間関係の構築が求められることで、慣れるまではエネルギーを消耗しやすい状況ですね。
特に、初対面の人との関わりや新たな上下関係の中では、「うまくやらなければ」「相手にどう思われるだろう」といった緊張感がつきまとうものです。これは無意識のうちに心身を緊張させ、自律神経にも影響を及ぼします。結果として、疲れやすさや気分の落ち込みといった不調につながる可能性があります。また、家庭においても、子どもが進級や進学で新しい先生や友人に囲まれることで、親子ともに対応が必要になる場合も。
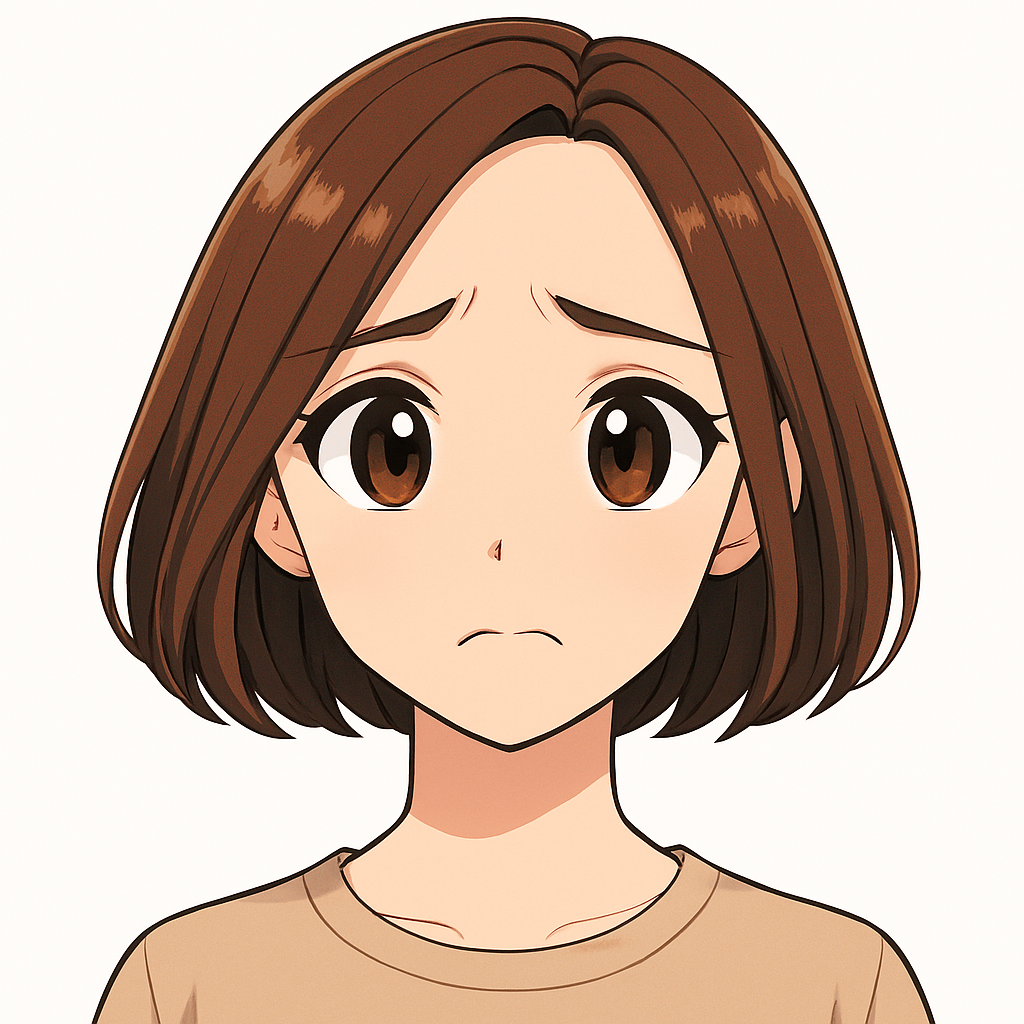
わが家の上の子も、ちょうどクラス替えと、それに伴い担任の先生も変わりました。連絡帳にあいさつを書いたり、荷物の準備のお知らせの仕方なども若干変わり、慣れるまではいつもより少しやることも増えそうです。
これらの変化に適応しようとする中で、体も心も常に緊張状態になってしまいます。この状態が長く続くと、交感神経が優位になり、睡眠の質が低下したり、消化機能が落ちたりと、心身のバランスが崩れがち。結果として、ゴールデンウィーク明けに「もう無理…」という状態になることがあるのです。
五月病を防ぐには、心身への負担を早めにケアすることが大切です。ポイントは「4月の過ごし方」。以下の3つの視点から予防策を見ていきましょう。

睡眠は自律神経を整える基本です。エネルギーの消耗が大きいこの時期には、特に意識して6時間以上の質の良い睡眠が必要とされています。しかし、厚生労働省の調査によると、睡眠時間が6〜9時間とれている人の割合は令和元年の調査で54.5%と半分程度です。ましてや4月のような新しい環境では、気づかないうちに緊張が続いたり普段よりもやることも多くなりがちで、意識をしないと十分な睡眠をとりにくい状況が続きます。できるだけ睡眠時間の確保と質の良い睡眠を意識して過ごすようにしましょう。
エネルギーを多く消耗するこの時期は、特に栄養バランスの良い食事が大切です。とはいえ、わかっていても忙しいこの時期は菓子パンやカップラーメン、コンビニ食など栄養が偏りがち。結局疲労の蓄積などにより五月病に繋がってしまいます。
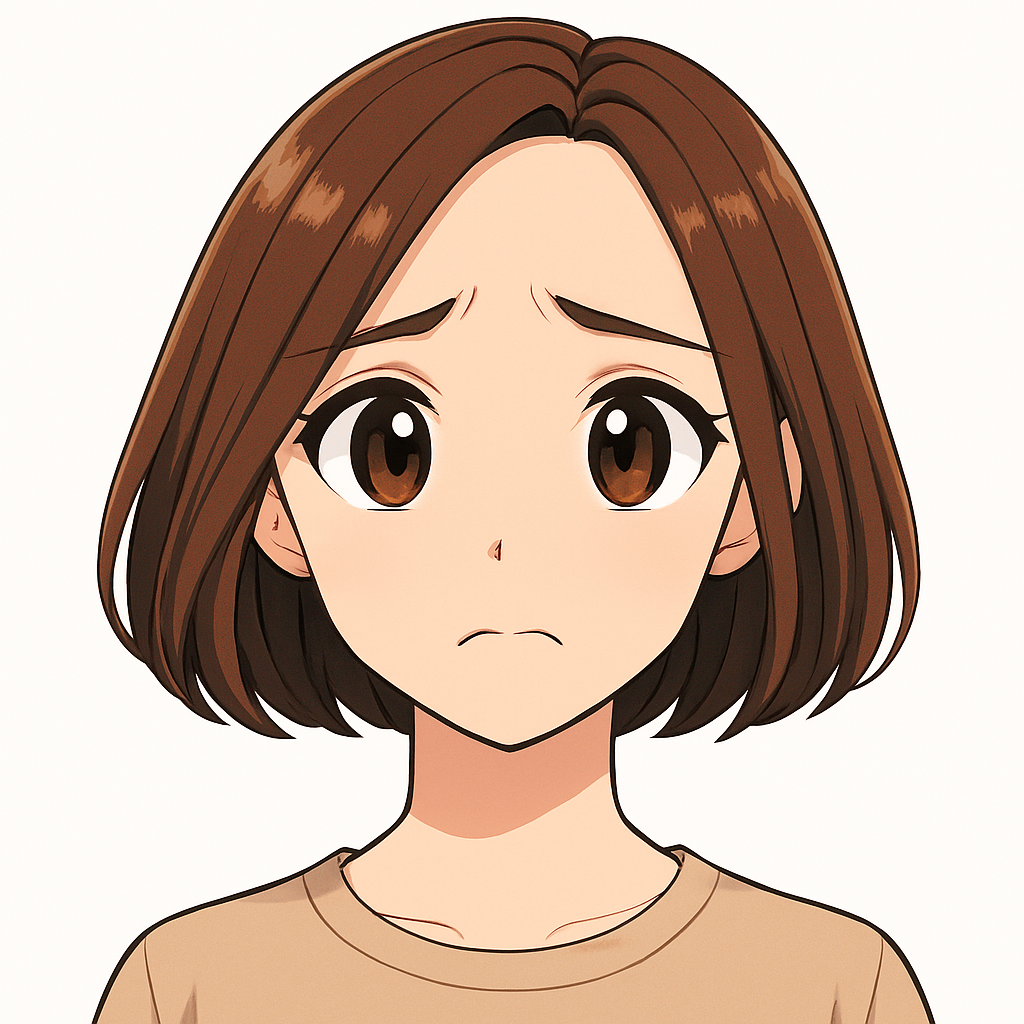
私も最近は忙しさや疲労感の強さから、実は普段よりもコンビニに寄る回数やスーパーのお惣菜を買う頻度が増えています。
| 栄養素 | 効果 | 含まれる食材例 |
|---|---|---|
| トリプトファン | 精神を安定させるセロトニンの原料となる | 赤みの肉・魚、鮭・さばなどの魚類、鶏むね肉、納豆などの大豆製品、牛乳・チーズなどの乳製品、ナッツ類、卵、バナナ など |
| ビタミンB群 | ||
| タンパク質 | ホルモンや免疫力を保つ | 鶏肉、魚、大豆製品、卵 |
| 食物繊維 | 腸内環境を整える | 野菜、海藻、きのこ類 |
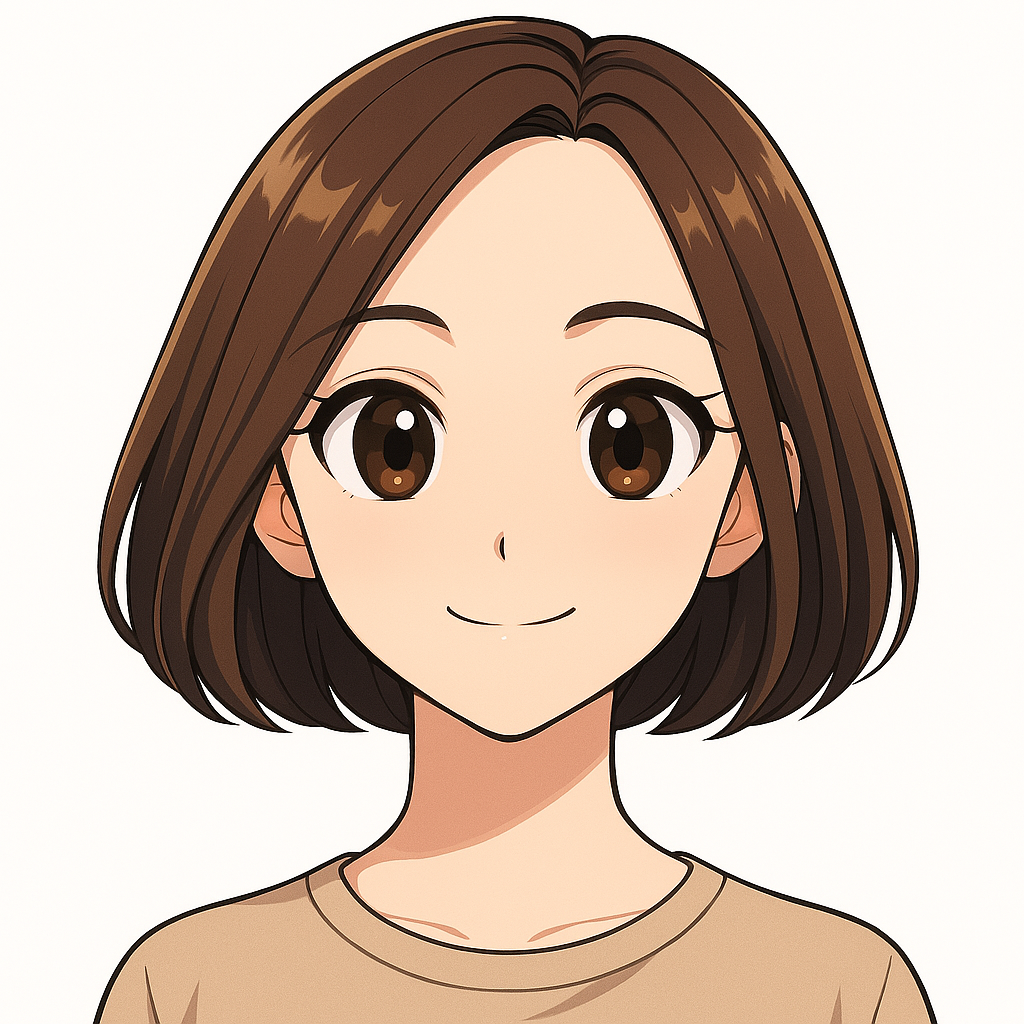
タンパク質や野菜など、バランスよく食べると良さそうです。
わかってはいるのですが、なかなか手間ひまかかるのではないでしょうか。
ごはんだけ朝炊いておいて、以下のものを選ぶと栄養バランスを整えることができます。

また、すぐに出せるもの、加えるだけで立派なおかずになるものも冷蔵庫にあると心強いです。

我が家は即席味噌汁を常備しています。エネルギーゼロの時は、白いごはんと味噌汁です。
子どもたちが一番喜ぶような気も。。。
近年話題になっている「完全栄養食」は、1食分で1日に必要な栄養素の3分の1を摂取できる食品です。”足りない部分を一品で手軽に補える”ことが最大の利点です。一食分の置きかえや普段の食事にプラスして不足分を補うなど上手に活用しましょう。
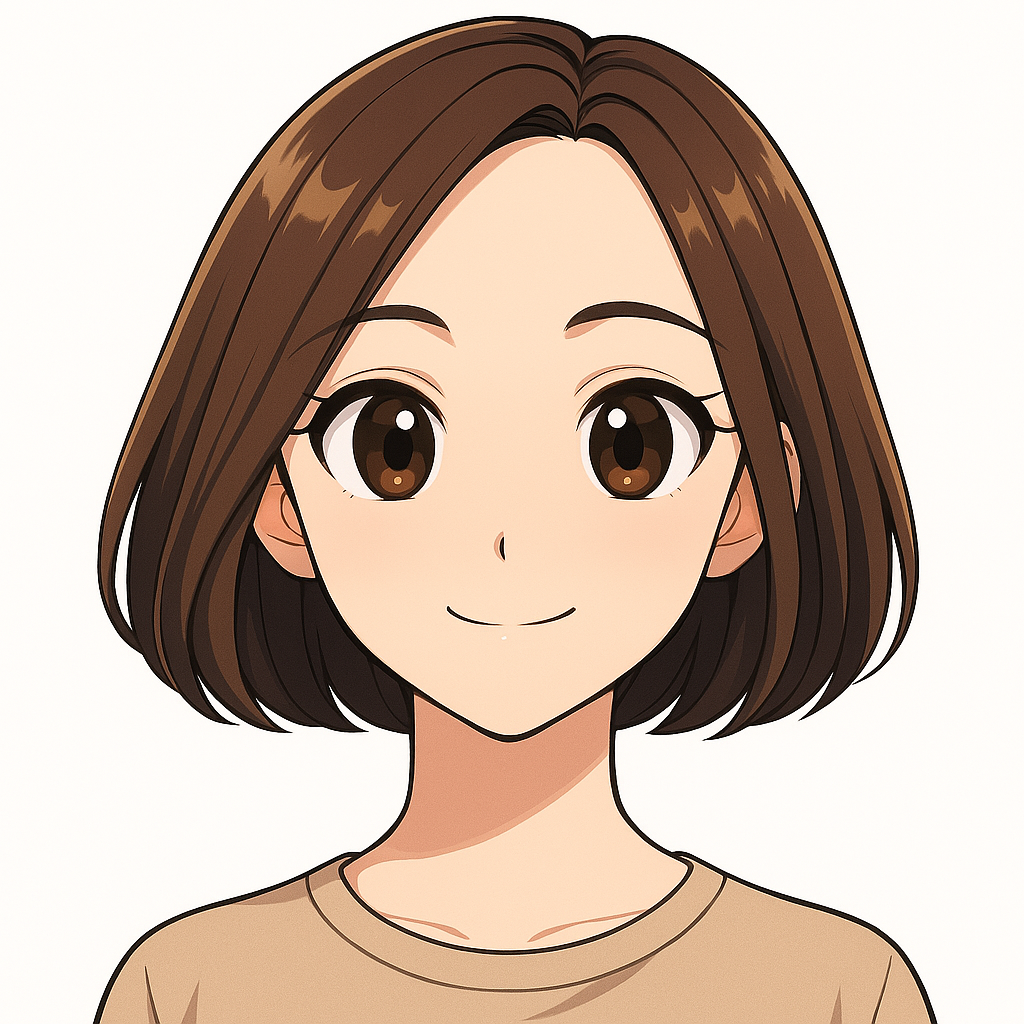
気になっている方も多いかと思います。コンビニですぐに手に入るものもありますので一度試してみてはいかがでしょうか。
私がよくコンビニで買っているのがBASE BREAD。チョコ味が美味しくて朝によく食べています。
子どもも大人も大好き。これ一品で立派な食事になるラーメンも完全栄養食がありました!おかずを作らなくていいので、これで一食ばっちりですね。
CMでもよくみる日清食品の完全メシは、食べなれたカップラーメンや焼きそばだけではなく、スープやパスタ、ドリンクと非常に種類が豊富です。いつも選ぶカップ麺ではなく、疲れがたまりやすいこの時期におすすめです。
リンク
昔から定番のカロリーメイトは、非常食用にも常に揃えるようにしています。ゼリータイプは冷やして夏の間食や補助食にピッタリです。
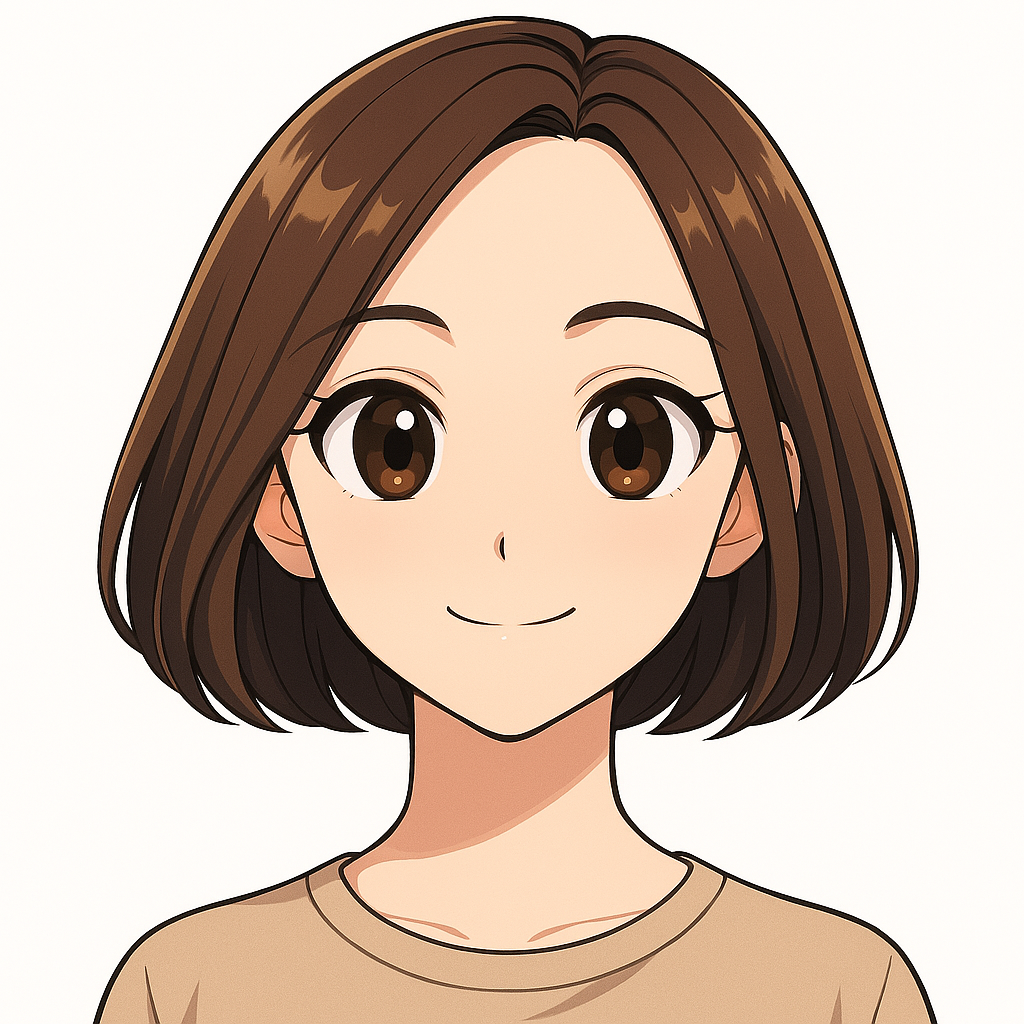
忙しいと食事がおろそかになりがちですが、体は食べたもので作られます。今の時期は味や満足感に合わせて、栄養面も意識した食事をとりましょう。
過剰な緊張が続きやすいこの時期に自律神経のバランスを崩さず過ごすためには、副交感神経を優位にして、緊張を緩める・リラックスする時間をこまめにとることがとても重要です。まさに五月病の大きな要因は、1ヶ月間ずっと緊張状態にあった精神状態がゴールデンウィークに一気に緩み、症状として現れてしまうことです。一度大きく沈んでしまうと、症状の回復にも時間を要してしまいます。
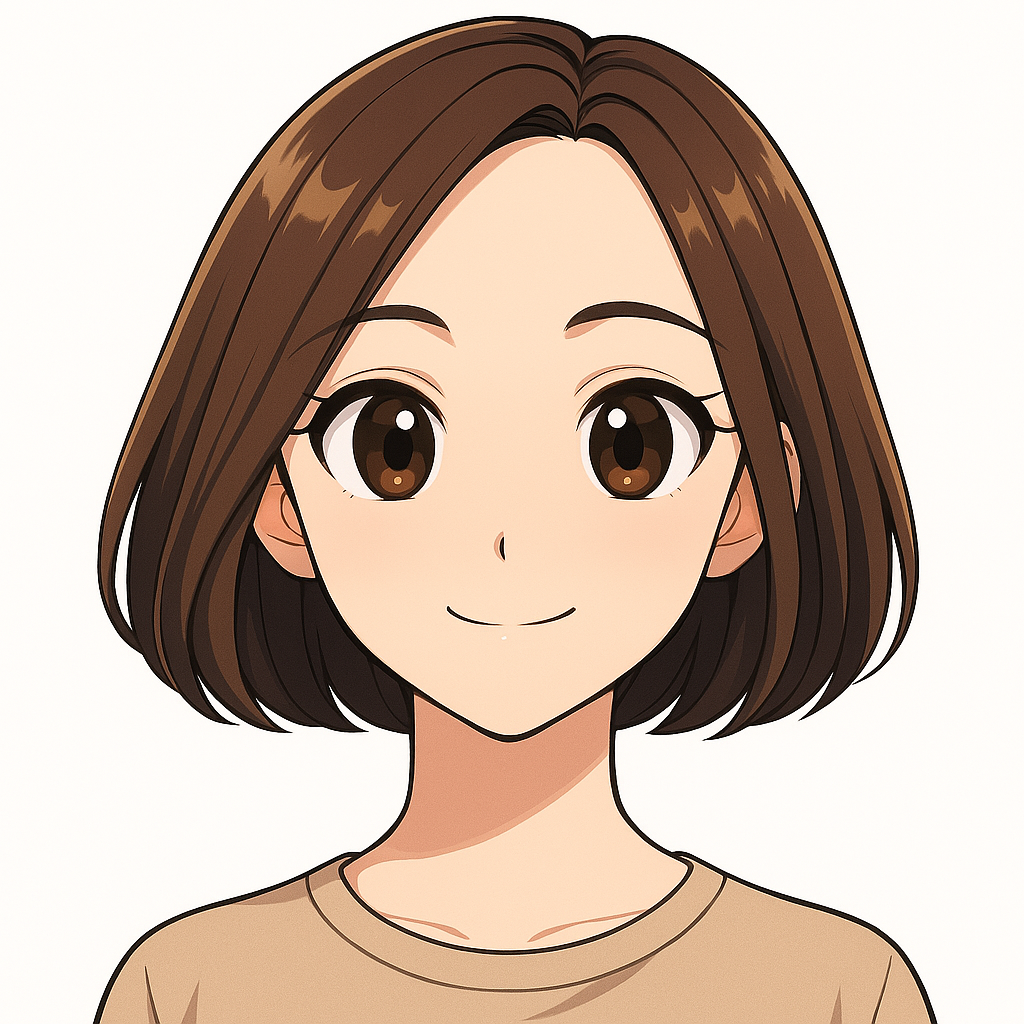
週末にたまった疲れをとる、ということもありますが、出来るだけ1日の中で短時間でも良いので、リラックスする時間を意識して作りましょう。
呼吸は自律神経と直結しています。意識して「吸う<吐く」をゆっくり繰り返してみましょう。3回でも変化を感じられます。
内臓からぽかぽかすると、自然と緊張がほどけます。
忙しい朝や夜寝る前に、ただ“飲む”ことに集中するのがポイントです。
お湯を入れるだけで白湯の適温に保ってくれるので便利
首・肩まわりが冷えてたり力が持続して入っていると、自律神経のバランスも崩れがちです。
蒸しタオルやネックウォーマーで首元をあたためると、副交感神経が働きやすくなります。
電子レンジでチンするだけで何度も使える優れもの。お腹が痛い時はお腹にあてています。女性には特におすすめです。
いつもより少しゆっくりめに歩いてみましょう。
足の裏を感じながら歩くと、意識が「今ここ」に戻ってきます。散歩に出られなくても、室内で5分歩くだけでもOK。
嗅覚は本能に直結します。また香りは瞬時に脳へ届きます。
ラベンダー、ベルガモット、ネロリなどがおすすめ。ディフューザーがなくても、ハンカチに1滴垂らすだけで◎
シャワーだけで済ませがちな日こそ、湯船につかることが副交感神経をオンにする近道。
38~40℃くらいのぬるめのお湯に、10〜15分。スマホは置いて、ぼーっと湯気を眺めるのもいい時間。
本を読んだり、スマホを置いたり、ゆっくりお風呂時間に便利なバステーブル。お風呂グッズは探すとたくさんありますね。
感謝の気持ちを表現することで、心がやわらぎ、リラックス状態に。
誰かに言えなくても、自分に「今日も頑張ったね」と声をかけるだけで、ホッと副交感神経にスイッチが入ります。
難しいポーズじゃなくて大丈夫。
朝起きた時や寝る前に、肩回しや前屈、深い伸びを取り入れるだけで血流が良くなり、身体も神経もゆるみます。
ふわっとしたものを抱きしめるだけで、オキシトシン(幸せホルモン)が分泌されて副交感神経が優位に。
誰かとハグできるならもちろん◎。ひとり時間なら、ぬいぐるみやクッションを抱いても同じ効果があります。
夜のスマホ、つい見てしまいますよね…。でもブルーライトや情報過多は交感神経を刺激します。
「寝る30分前にスマホを手放す」と決めて、代わりにお気に入りの音楽や読書を。脳も身体も安心して眠りにつけます。

色々試して過ごしてみても、ゴールデンウィークあたりから「なんとなくやる気が出ない」「朝、起きるのがつらい」「食欲がない」「人と話したくない」などの症状が2週間以上続く場合は、心のサインを見逃さないことが大切です。無理はせず早めに対処しましょう。
無理をして頑張りすぎると、症状が悪化してうつ病などにつながることもあります。心療内科やメンタルクリニックに受診して相談しましょう。我慢して、どんどん無理を重ねると、その何倍も回復に時間を要してしまいます。もしかしたら・・・と思ったら、早めに相談することで早期回復が見込めます。
五月病は突然やってくるものではなく、4月からの心身の疲れやストレスの積み重ねで引き起こされるものです。だからこそ、4月の過ごし方がカギになります。
特に忙しい方こそ、自分自身のケアを後回しにしがちですが、まずは自分が元気でいることが、家族の笑顔と生活の安定につながります。